日経BPマーケティング社 様より献本御礼。
技術をとことん極めると、頂点のようなものが見えてくることもある。それが見えたとき、達成感と同時に、途方もない空しさが襲うようになる。そこから「飽き」が生じ、新たなことを始めようとする。
自分自身も飽きっぽい性格であり、技術や興味がある程度まで達すると、とたんに「何をやっているのだろう?他にやるべきことがあるのでは」と思ってしまい飽きてしまうことが度々あった。
しかし「飽きる」という感情はなにも悪いことではない。むしろ新しいチャレンジを行うためのカンフル剤であり、新たな果実を見つけるチャンスでもある。
本書は「飽きる」ことこそこれから生き残るための「武器」になることを説きつつ、変化や成長の重要性について語っている。
第1章「成長は、ある日突然やってくる―1976年、10歳」
父親の転勤で何度色々な場所に転校することになった著者の少年時代。天候のなかにはアメリカに渡ることもあった。日本とは全く異なる風土、文化、言語、そして何よりも学校の授業は日本のそれとは全くことなり、衝撃を受けたという。そしてそこで学んだことは後の人生のなかでの大きな糧となった。
第2章「正しい解き方より正しい疑問―1987年、21歳」
日本の教育には一つの答えを求めたがるのだが、アメリカやイギリスの教育では、答えが複数あるようなものもあれば、無いものもある。
著者は大学で医学を専攻したが、医学研究のなかで正しい解を見つけることよりも「疑問」をもつことを学んだという。その研究は斬新なものであり、かつ研究のプロセスもまた斬新なものだったという。
第3章「苦手なことは他流試合で突き破る―1996年、30歳」
経験不足から大学病院から、別の病院に移籍した。その病院は「名医」が多数在籍する病院だったが、厳しい修行を行い、一目置く医者となった。同時に医学研究にも勤しんだが、研究のなかでバイオベンチャーにも目を向き始め、そして実行に移していった。
第4章「庭先の穴を掘っても石油は出ない―2002年、36歳」
本章のサブタイトルである2002年にバイオベンチャーとしてビジネスをスタートさせた。しかしそのときはITバブル崩壊で経済が停滞していた頃。資金集めも奔走する毎日だった。ようやく資金調達ができたとき、ビジネスモデルをもとに試行錯誤を重ねた。しかし、ビジネスモデルが破綻を喫してしまった。その破綻から打開すべく、さらに資金調達に奔走し、ビジネスモデルを変化をしながら試行錯誤をひたすら繰り返した。
第5章「「想定外」こそ面白い―2013年、47歳」
試行錯誤を繰り返すなかで、大手製薬会社と国際共同開発も行われ始めた。研究のなかでは戦略やイノベーションが絶えず行われており、それによる社内体制の変化も大きく、迅速になっていった。
生き残るためにはまず「変化」をしなければならない。
その言葉を忠実に守るがごとく。
著者は研究員を行い、医者になり、そしてベンチャー企業の社長も行った。全くことなる道を突き進んだ、のかと思いきや、基軸がある。一つは「医学」、そしてもう一つは「眼」である。
書き忘れてしまったのだが、著者が先行したのは医学のなかでも「眼科学」と呼ばれるものであり、医者も「眼科医」となった。そして、ベンチャー企業で開発する薬も、「眼科治療薬」の開発である。その上で著者には「眼」を通じた最終目標がある。
それは「世界中から失明をなくすこと」
この「基軸」があるからでこそ、様々なチャレンジを行い、変化を恐れず突き進んでいった。そしてその道はこれからも続く。



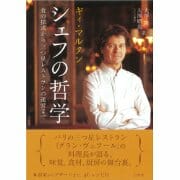
コメント