本書のサブタイトルには「ノマドロジー」である。 最近言われている言葉に「ノマド」という言葉があるのだが、これはあくまで「遊牧民」を表す言葉であるのだが、その「ノマド」について哲学的見地から考察を行ったこととして「ノマドロジー」があり、それを初めて考察したのがジル・ドゥルーズだったのだという。
本書はドゥルーズの生涯とともに、哲学者として、小説家としてどのような影響を及ぼしたのか、そして、「ノマドロジー」という考え方をいかにしてつくられたのかを取り上げている。
第一章「哲学者たち」
ジル・ドゥルーズは1925年にパリで生まれたが、彼が15歳のナチスドイツのパリ侵攻により陥落してしまったとき、兄を失った。そのことがきっかけとなり哲学者となってからは同じ境遇に遭った哲学者・サルトルの哲学にも多大なる影響を受けた。1944年にナチスドイツから解放されると(パリ解放)、ソルボンヌ大学へ行き、本格的に哲学を学び始めた。その後教授資格を得て、1957年に古巣であるソルボンヌ大学で助手を勤め、哲学者人生をスタートさせた。その頃の著者の研究対象はニーチェやベルグソン、スピノザ、ヒューム、カントなどの哲学の違いとは何かを整理していたところにあった。
第二章「小説家たち」
1960年代に入ると、小説作品と哲学との関係性の研究を始めた。その時の研究対象は「失われた時を求めて」で有名なマルセル・プルースト、さらに「S(サディズム)」と「M(マゾヒズム)」を生み出したマルキ・ド・サドとザッヘル・マゾッホの性癖について哲学的な見地で研究を行ったのだという。ある種の「臨床医学」ならぬ「臨床哲学」というべきか。
第三章「差異と反復」
先進国を中心に1968年は「激動」と呼ばれる年だった。日本では「大学紛争」「ベトナム戦争反対運動」、アメリカでは「ベトナム戦争反対運動」「公民権運動」、そしてフランスでは「五月革命」と呼ばれる学生革命が起こっていた。その原因には「反政府運動」が起因していた。
この革命についてドゥルーズは衝撃を受け、肺の障害に苦しんだ。その時期にスピノザ哲学の研究に勤しみ、人間の同一性の研究も同時に進めていた。同一性の研究のなかで名著である「差異と反復」という論文を発表した。
第四章「機械圏へ」
ドゥルーズはパリの第八大学の教授になった。その時の教授メンバーにはフーコーもおり、フーコーの私淑を受けた。同時に数々の共著を生み出すパートナーとなるフェリックス・ガタリとの出会いもあった。その2人が共著としての対策「アンチ・オイディプス」を生み出したのはであってから3年後の話である。
第五章「ノマドロジー」
本章で言う「ノマドロジー」というのは、
「遊牧民的生活の復権を目指す思想。権力を嫌い、境界を越えて流動し、多様な生活を同時に生きることなどを唱える。」(「コトバンク」より)
とある。この言葉と意味が初めて使われたのは1980年にガタリとの共著「千のプラトー」だった。戦争にしても、資本主義にしても、専制君主にしても「機械」の様にあった。その機械は「遊牧民(ノマド)」がつくりだし、様々な環境を作り込んだのだという。
第六章「イマージュ論」
最後は「イマージュ(想像)」の世界について、1980年代に研究を進めていた「映画論」について考察を行っている。なぜ、ドゥルーズは「映画論」を世に送り出したのだろうか。そこには「千のプラトー」や「アンチ・オイディプス」の研究している最中に沸いて出た疑問として絵画や映画などの背景にはどのような「機械」があるのだろうか、「機械」によってどのような「イマージュ」が生まれたのだろうかという疑問から出てきた産物である。
戦後フランス哲学のなかでも燦然と輝く哲学者の一人であるジル・ドゥルーズだが、晩年は肺の病気が悪化したことに絶望し、1995年に自宅から身投げして自決してしまった。ドゥルーズの哲学は様々な哲学批判から始まり、「同一性」の定義、映画、資本主義やノマドロジーの概念、そして晩年は自分自身の体験をも哲学として昇華した。様々な哲学を「反復」しながらも自らの哲学を定義し、そして新たな哲学を生み出した。その功績は今も色褪せる事は無い。



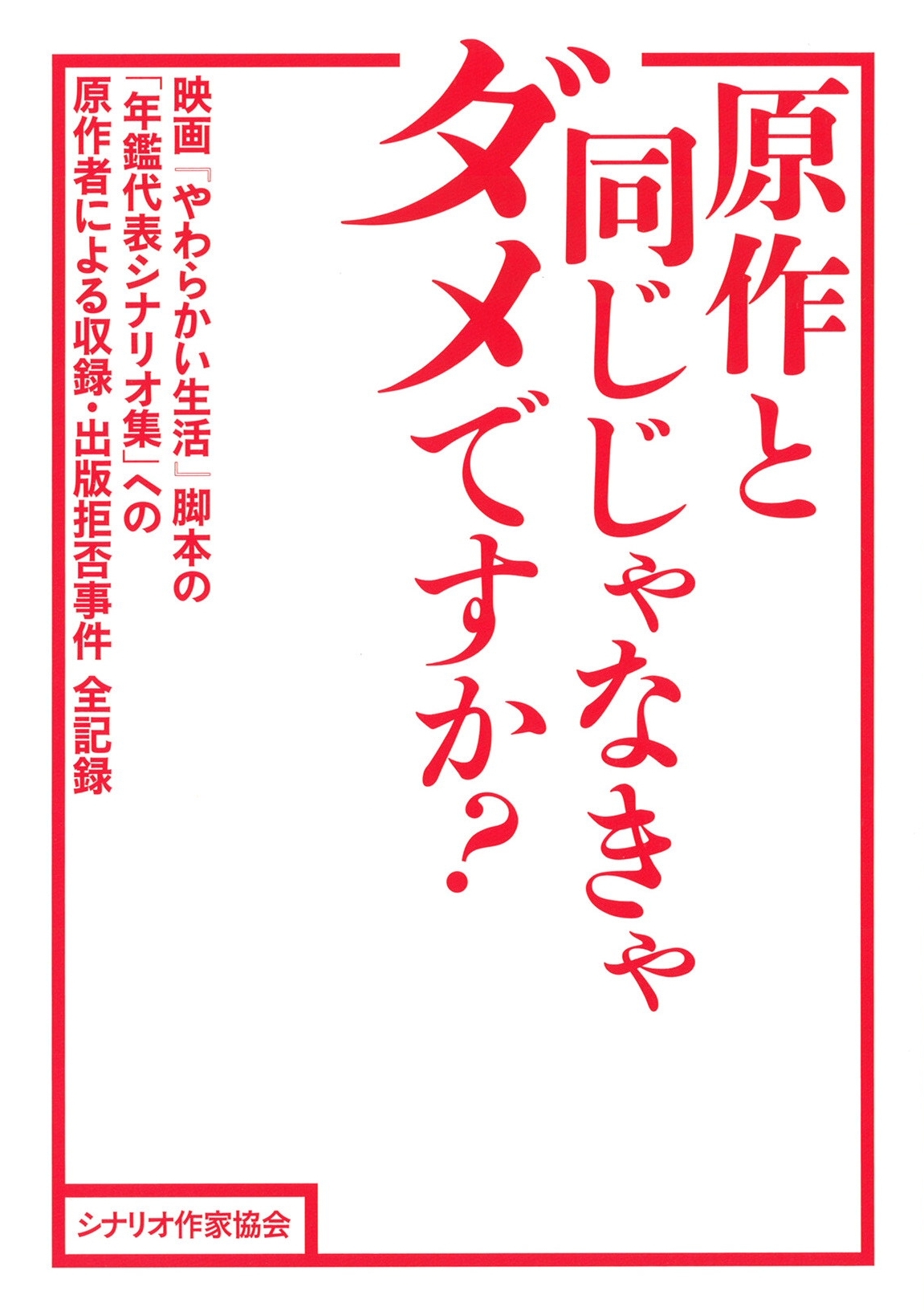
コメント