捕鯨問題というと、オーストラリアの反捕鯨の声が鋭くなった。それは今年の5月にオーストラリア首相にケビン・ラッドが再登板したことにある。日本では伝統的に調査捕鯨を行われており、刺身や加工食品などに使われており、需要はある。
捕鯨を行っている国は日本だけでは無く、ノルウェーもあれば、本書で取り上げるインドネシアもある。インドネシアの中でもレンバタ島と呼ばれる小さな島村では銛だけで鯨を仕留める捕鯨があり、19年にもわたって島の食と文化を支え続けた。本書はその捕鯨までの道筋を写真とともに綴っている。
第一章「鯨の島へ」
著者は元々通信社のカメラマンだったのだが、会社を辞め、フリーランスとなった。そのフリーランスになった時の最初の撮影がこのインドネシアの捕鯨の撮影である。情報化社会と言われ「秘境は存在しない」と言われている中で、インドネシアで伝統的な捕鯨を行っている「秘境」に巡り会い、取材を始めた。
第二章「鯨漁に挑戦」
著者が取材したラマレラ島という島は東京から出発しても最低3日かかるほどの所にある。そのため、観光目的ではほとんど行かないような所と言っても過言ではない。
著者はラマレラ島に到着し、捕鯨を行う漁師とも会うことになり、翌日には出漁することになった。ラマレラ島の捕鯨は日本のようにハイテクな機能を持った船のレーダーで探知する、と言ったことはできない。全て漁師の感覚が全てを握っていると言っても過言ではない。しかも鯨は毎日釣れるとは限らず、数日かけても1匹も採れないこともざらにあるのだという。
ちなみにこの日は1匹も採ることはできなかった。
第三章「再挑戦」
再挑戦をする前に、新たに捕鯨用の船を作る必要があった。そもそも船を作ることも捕鯨をするために大事な事は明白であるのだが、船そのものは漁師がつくると言ったものだった。
再挑戦を行うまでの間に船を造る、造っている間にお祭りがあり、村民達の話を聞いたりしたのだという。その中で捕鯨は死と隣り合わせであることを知ったのだという。元々銛一本で捕獲するので、鯨が暴れると、漁師の身に危害が及ぶ可能性がある。現に尾びれをはたかれて亡くなった漁師もいたのだという。
またラマレラ島の方々が語る旧日本兵の姿もここでは取り上げられている。平氏の中には嘘をついたり、殴ったりする人はいたが、ほとんど殺しはしなかったのだという。したとしても、現地民が泥棒を行ったり、放火をしたり人だけだったという。
第四章「鯨漁撮影」
再挑戦を繰り返しながら数年経ったのだが、ようやく鯨を捕ることができる事ができたと言う。その鯨漁ができた写真をふんだんに盛り込まれているが、そこには鯨漁の瞬間、そして漁の後が映っていたが、一人で漁に向かっているわけでは無く、船を漕ぐ人が何人もいるという「支え」なくして、漁は成り立たないのだという。
第五章「陸の物語」
鯨を捕ることができたら、今度は解体を行い、鯨肉から内臓、骨、歯に至るまで分解し、交換資源として、あるいは食用として分配されるのだという。
第六章「鯨の眼」
鯨漁をする際に、鯨がいることを見抜く眼を鍛えるには一朝一夕では無理である。もっと言うと数年、ないし10年以上の時間を要している。
話は変わるが、眼と言えば、本章ではなかなか撮ることのできない「鯨の目」を取り上げている。
日本やノルウェーの捕鯨についてはよく知っているのだが、インドネシアの漁については初めて知ったことと、それと捕鯨の瞬間の写真や鯨についての写真がふんだんに盛り込まれている所が魅力的な一冊であった。
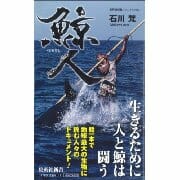



コメント