日本には「恥じらい」の文化がある。その一方で開けっぴろげな絵や作品も少なくなく、「恥じらい」を持っていたり、持っていなかったりと曖昧である。その「曖昧さ」が日本語にもあるように、日本文化を象徴であるとともに、曖昧であることへの魅力も存在する。
本書はその中でも「恥じらい」「恥ずかしさ」がいかにしてできたのか、そしてその「恥」はいったいどこに向かっているのかに対して考察を行っている。
第一章「<恥ずかしさ>のいま」
「恥」としてもっとも語られるものとして「羞恥心」である。かつてある芸能人がプロデュースしたユニットがあるのだが、そうではなく、今生きていることが「みっともない」と思って「羞恥心」を取り上げている。
第二章「恥感覚と起動原理」
日本が「恥」の文化であることを初めて記したのが、ルース・ヴェネディクトの「菊と刀」である。欧米諸国、もっというとキリスト教を中心としてる国々の「「罪」の文化」の対比として表されたのだが、「文化」の上下について論じた人もいれば、日本にしかない文化であることを語っているのだと表した論者もいた。
ともあれ、古来から根付いている「恥」について、「罪」と対比しながら、その原理を追っている。
第三章「「話すこと」の負い目」
言語が違えど、ほどんどの人間には「話す」能力が備わっている。その「話す」ことで言葉のやりとりができ、それがキャッチボールとなり、コミュニケーションとなる。
しかしその「話す」は時として「罪」や「恥」をつくることもある。それが「負い目」に転化するとなる。
第四章「<恥ずかしさ>の復権」
本章のタイトルにある「復権」の鍵として「壁」と言うのがある。その「壁」は形のある壁ではなく、心の中など見えないところでの「壁」についてを語っている。
「恥ずかしさ」「恥じらい」はいったいどこからきたのだろうか、という問いには「哲学」というより「文化」という言葉が似合っているのかもしれない。日本にある「恥の文化」もしかり、キリスト教の国でも「罪」からくる「恥」があるように、宗教や哲学の思想に惑わされることのない「文化」の感情としての「恥」がある、と本書では言っているのではないだろうか。


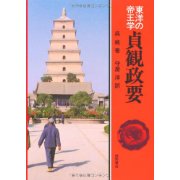

コメント