日々の生活において「ルーティーン」は欠かせない。もちろんルーティーンも変化をすることも大事であるが、体内のリズムを整えるために意識して良いルーティンを回し続けることも必要である。ではどのようなルーティーンを行う事で、太らず、病気にならないようになるのか、本書はトレーニングをはじめとした習慣を中心に取り上げている。
1章「健康はすべて「腸内環境」が決める」
「腸活」と言う言葉がある。特に腸内環境を良くするための衣食住の習慣を改めるというような活動である。その「腸活」を支えるものとして「腸内細菌」があるのだが、生活習慣病の多くは腸内細菌の「異常」によって起こると言う。ではその「異常」をどのように「正常」にして行くのかを取り上げている。
2章「脳をだます「習慣化」の重要性と、7つの作戦」
日々健康的に生きるためには、日々の「習慣」を変えていく必要がある。ではどのような事を「習慣化」すべきなのか、本章ではそのことについて取り上げている。
3章「頑張らない「筋トレ」が万病を防ぐ」
「筋トレ」すると言っても、ジムでトレーニングをしたり、筋トレグッズなどを用いて、筋力を上げるようなイメージを持たれるのだが、本章以降における「筋トレ」は「頑張らない」ことが念頭としてある。もっとも筋トレ自体も「続ける」ことが大事であるが、この「頑張らない」こそムリなく続けることの要素である。
4章「初級実践 1日からすぐに始められる健康習慣10&筋トレ30秒」
この筋トレについて本章から6章にかけて3段階で取り上げている。本章はまず初級編として、筋トレ初日から行う生活習慣と筋トレメニューを紹介している。特に筋トレは「30秒」だけでよく、「続ける」ためのきっかけ作りとして挙げられる。
5章「中級実践 2日間の「ボーンブロスファスティング」&筋トレ2分」
本章のタイトルである「ボーンブロスファスティング」は、数年前に取り上げた「ボーンブロス(骨スープ)」を使った「断食法(ファスティング)」を表している。レシピについても具体的に言及しているため、どのような食材が必要なのかをリストにして購入して、作っておくと良い。またそのうえで、中級編としての運動として何が必要なのかを取り上げている。
6章「上級実践 28日間の「間欠的ファスティング」&HIITトレーニング4分」
特にエクササイズにおいて「HITT(High Intensity Interval Training:高強度インターバルトレーニング)」を取り上げつつ、週に数回ファスティングを行う方法がある。もちろん断食であるが、全ての食をファスティングするわけで無く、部分的にファスティングを行い、それ以外は食事を行う。しかしファスティング以外の食事についてもどのように行うのかも網羅している。
本書を見ていくと、「太らない」と言うよりもむしろ「ダイエット」という意味合いが強いように思えてならない。もちろん身体的なトレーニングは日々の健康的な生活を行う中で重要な要素になるためトレーニングはけっこう参考になりやすい。もちろんトレーニングにしてもファスティングにしても習慣化することによって身体的な変化は起こることは間違いないのだが、個人差があり、なおかつ本書を忠実に実践を行うとなると、周囲に宣言する、あるいは日々SNSなどで取り上げるなどある種の動機付けを行わないと非常に難しい様に思えてならない。

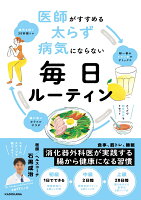


コメント